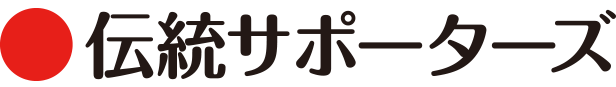時を超えて100年、1000年朽ちない後世に残せる作品を世に出したい
河野玄容(こうの・げんよう)/陶芸家(砥部焼)
愛媛県西予市宇和町出身、1952年生まれ。日本伝統工芸展・日本陶芸入選・全陶展常任審査員・常任理事・同四国支部長。大阪芸術大学 芸術学部 デザイン学科 ID(インダストリアルデザイン)専攻卒業。日本伝統工芸展や日本陶芸展など数多くの入選歴を誇り、全国陶芸展の常任理事として審査員も務めている。四国有数の窯場として栄えた松山市平井町で作陶し、日々新たな作品を送り出している。一方、インテリアデザインとディスプレイデザインの分野の経験も豊富で、陶芸およびディスプレイデザインの両分野で国定検定一級技能士の認定を受けている。
私が陶芸家として作品を創る上でのこだわり、それは古いものをコピーするのではなく、洋風モダン空間に映えるような、新しい時代にふさわしい作品を創ること。
砥部焼(とべやき)といえば、私の地元愛媛県を代表する陶磁器です。
そのイメージは「重くて丈夫」「丼鉢」といったものばかり。
私はこうしたイメージを払拭するためにも、日々ろくろと向き合っています。
そして、大量生産ではないカタチ。
百個作っていくらという仕事ではなく、一個からでも大事に、価値のあるものを創っていきたいと、切に思います。
デザイナーのキャリア重ねるうちに見えてきた新しい夢

小学生時代の夢は、車のデザイナー。
その夢は中学、高校でも色あせることなく、大学も工業デザインを学ぶため、地元を離れて大阪芸術大学へ進みました。
そして、大学卒業を控えた時期には、念願だった愛知県の大手自動車メーカーへの内定をいただくことができました。ところが、当時発生したオイルショックが原因で、内定が一時保留、就職無期延期という知らせが…。
そんな知らせを聞いて、途方に暮れていると、家族にも「車にこだわらずに、他のデザインの仕事を探してみてはどうか」と心配され、他の仕事を探し始めたのです。
すると、たまたま地元(愛媛県松山市)にインテリアデザイナーを募集している会社があり、面接を受けてみたところ、採用という結果を受け、デザイナーとしての一歩を踏み出すことになりました。
そこは、当時スタッフが少なかったこともあり、任される仕事も多く、とても楽しく、有意義な仕事だと感じていました。ときには、とある店の改築に伴い、建築デザインや設計の責任者までやらせていただいたこともあります。

このようにデザイナーとしての仕事をこなしていく中で、私はぼんやりと頭の中で思い描いていた計画がありました。それは、地元の名産である砥部焼を、モダンな形でデザインをして創ったら…というものでした。
それからというもの、砥部焼の窯元を巡ったり、自ら陶芸を体験してみたり、陶芸の研究を重ねるようになったのです。
師匠・近藤先生との出会い、愛媛から京都まで“通い”修行

陶芸の研究を進めていく中、愛媛県松山市のとある画廊で近藤潤(こんどうひろし)先生という方が個展を開催されていました。この方こそ、後の私の師匠であり、私と師匠の初めての出会いでした。
たまたまこの画廊の運営を担当していた会社の上司が、ふと「河野君はデザインのことは分かっているだろうから、先生を砥部町へ案内してくれないか」という依頼を受けたのです。

自分も陶芸について、多少はかじっていたものの、陶芸作家がなんたるかもよく理解していない中、先生を車でご案内していきました。すると、先生は砥部焼の資料館に向かってくれとおっしゃいました。
その資料館には、先生のお父さんであり、人間国宝でもある故近藤悠三(こんどうゆうぞう)氏の作品が展示されており、その作品を一度ご覧になりたいとのことでした。
そうして案内をしている車中で、私は「焼き物に興味があるんですが、教えてもらえませんか」とお尋ねしたところ、先生は「京都に来る時間があるなら、いらっしゃい」と言い、名刺を頂きました。
それから約1ヵ月後、私は仕事の合間をぬって京都へ出向き、先生をたずねることにしました。
先生のお店に到着すると、先生の奥様が出迎えてくれ、私が「愛媛の松山から先生を訪ねてきました」と言うと、「お上手やわ~」と笑われてしまったことを覚えています(苦笑)。まさかそんな遠方から来るとは信じてもらえていなかったようです。
その後、先生にお目通りがかない、正式に弟子入りさせていただくことになりました。
しかし、このときの私は非常に生意気な若造でして、先生のお店に展示されておりました、先生のお父様の作品を拝見した際に「しめた!これなら私にもできる!」と勘違いしていました。
というのも、近藤先生の作品は、激しいタッチで、殴り書きのようなデザインが特徴であり、当時の無知な私からすると「ヘタウマ」という印象だったのです。
まぁこんな馬鹿で甘い考えは、修業に入った途端に間違いだったと、すぐさま思い知ることになったのですが。
また修業といっても、私はデザイナーとしての仕事を辞めていたわけではないので、月に3回京都へ通って勉強をさせていただいておりました。仕事を終えてから、夜に愛媛県を出発し、適当に買った巻き寿司を食べながら、夜通し運転をして朝方京都へ到着、それから修業。当時、瀬戸大橋もなかった時代でしたから、京都までの道のりは非常に大変でしたね。
約2年間通い続けて技術を習得していったのですが、先生の下で修業をしなければ、今の自分はなかったと思います。
近藤一門(いちもん)は、人間国宝である故近藤悠三氏の流れをくみ、近藤潤先生が受け継ぐ、日本のトップレベルの仕事をします。ろくろにしても、絵付けにしても当然高いレベルが求められます。そんな高い基準の中に、身を置くことができたのは、とても幸せなことでした。
本物の仕事のなんたるかを勉強させていただきました。
これが他の先生の下で修業していたら、ちょっと小器用な職人で終わっていたのではないか、と思います。
だからこそ、先生との出会いは私自身の人生にとって、大きな転機となりました。
後継者育成、若手作家輩出に力を言える地元・砥部の町

師匠の下で勉強した後、玄彩窯(げんさいよう)という窯元を開いた私は、それから約30年にわたって焼き物を創り続けてきました。おかげさまで、多くの弟子を育成する機会にも恵まれ、弟子たちの中には独立してプロとして活躍している方もいます。
ドイツから20代の女性が、手紙を送ってきて、日本へ行くのでぜひ陶芸を教えてくれと言ってきた、熱心な外国人の方もいました。その方も、2年間修業をして、日本で個展を開催するまでに成長し、現在はスイスで陶芸家として仕事をしていると聞いています。
とても嬉しいことです。
一般的に陶芸家になるには、先生に弟子入りするか、大量生産している企業の窯元に就職するか、職業訓練学校へ入るか、といった3つのパターンが多いです。しかし、砥部の町では行政とタッグを組んで、陶芸家を目指すタマゴたちに、職人たちが手弁当で教えあう、いわゆる講習会を行う活動が多くあって、若者たちが陶芸家を目指しやすい環境が整ってきています。
もちろん、世襲(特定の地位や職業を、子孫が代々承継すること)だけではなく、よその土地の人がやってきた場合でも、支援する制度がある。
陶芸家同士がライバルでけん制しあうような、ギスギスした関係ではなく、お互いに助け合って砥部焼を盛り上げていこうという考えなのです。
周りの人に支えられながら、人材が育っていく。
そうした中から、砥部焼の未来を担う若者が誕生することを、願っています。
「いつも一緒にいる気分」「買うのを楽しみに積み立て」
私はこの何十年の間で、何万個もの作品を創ってきました。
喜ばしいことに、その中の作品のほとんどが、私の手元から離れていっています。
そんな中でも、非常に印象的だったお客様との出会いが二つあります。
一つ目の出会いは、岡山で毎年開催している個展でのことです。
その個展で、膠原病(こうげんびょう)と呼ばれる難病を患った一人の女性と出会いました。
まだ若いのに杖をつきながら、私の個展に何度も足を運んでくださって、見かけるたびにお体を心配しておりました。
そして、個展のときに、私の作品をその女性が買ってくれて、偶然お話をする機会があったのです。
すると女性が「河野さんの作品を集めているので、一度自宅にこられませんか」とおっしゃってくださり、私はその女性の家にお伺いました。
驚いたことに、そこには私の作品が何十点とコレクションされていたのです。
私はついつい「どうしてこんなにも私の作品を集めていらっしゃるのですか」と聞くと、女性は「私といつも一緒にいてくれるような気持ちになるからです」とおっしゃいました。
その女性と私は直接のお付き合いはなく、何度か個展で会っただけの間柄だったのですが、女性は私の作品を心の支えとしてくれていたのです。そして、その女性はこのコレクションを大事にしながら、亡くなっていきました。残された家族の方にも、作品はとても大事なものだから手放さないように、と言っていたそうです。
この出来事は、いつまでも忘れることはできません。
もう一つは、とある独身女性が私の作品をずっと集め続けていらっしゃったそうです。
そして、お嫁に行くときの嫁入り道具として、私の作品を持っていかれたそうです。
その器は新婚生活でも使われ、その後も毎年20年間にわたって買い足していただいて、ほとんど私の作品で食事を楽しまれていると聞きました。
これを聞いたとき、まさに職人冥利に尽きると思いました。
お金持ちの方が、パッと来られてパッと買われていくのも、それはそれでもちろん嬉しいものですが、一般の主婦の方が「作品展はまた来年ありますか?」と聞いてこられ、「はい、来年もやらせてもらいます」と答えると「作品を買うために、毎月3000円ずつ積み立てして、へそくりしていますのよ」なんておっしゃってくださる方もいらっしゃいます。
そして、次の年に買いにきてくれる。
こうしたお客様は、とてもありがたいと思いますね。
窯を開ける瞬間の胸の高鳴り、”火の洗礼”は最大の魅力
焼き物は、成形して、乾燥させ、素焼き(低温で焼くこと)を行い、薬を掛けて、最後に本焼きといって1,200度以上の炎でたき上げます。
ここで、火の洗礼を受けるのです。
一生懸命創った作品も、火の神様のいたずらでヒビが入ったり、薬がうまくかからなかったり、自分の力が及ばないところでいろんなことが起きます。それをコントロールするのが職人としての腕なのかもしれませんが、出たとこ勝負のところが大きいのです。
これは良いものができるぞ!と思って焼いたものが、窯に入れると残念な状態で窯から出さなければならないことも、少なくありません。逆に、思わぬ良いものができることもある。そんなときは、火の神様が味方してくれたのかな、なんて思いますね。
だから、窯を開ける瞬間というのは、何度やっても胸が高鳴ります。
これは陶芸の最大の魅力かもしれませんね。
そして、1200度という何もかも焼き尽くす炎の中で生まれた焼き物は、まさに炎の力で完成された作品です。こうして完成された焼き物は、割れない限りは1000年以上持ちます。
金属や木で作られたものであれば、そのどちらもが1000年も経てば朽ちてしまいます。
ところが、焼き物は朽ちないのです。
だからこそ、本当に良いものを創って、後世に残せるものを、一つでも二つでも生み出せたらいいなと思います。私がいなくなったとしても、時を超えて何百年、何千年と受け継がれて大事にしてくれたら、そこに生き続けてくれる。
これはとても嬉しいことだと思います。